« はじめてでも大丈夫!『いちから始めるインドカレー』 編集担当者より♪ | TOPページへ | 『簡素なお菓子』 Part 4 »
2011年06月28日
料理本のソムリエ [ vol.24 ]
【 vol.24】
忘れられた「花の茶屋」
へっへっへっへっへえ、手に入れちゃいましたよ! 昭和2年10月刊行の「花の茶屋」の機関誌『味冴』5周年記念号! 古書即売会の出品目録をめくっていてこの二文字にぶつかったときは、思わず二度見しちゃいましたよ。会場に並ぶ商品と違って目録掲載品は抽選なものだから、申し込んでから2週間、当りますように当たりますようにと、ずうっと落ち着かなかった。やれやれ、これでひと安心ってなもんだ。
にたにた気持ち悪いですって? だってこの雑誌、あたしの知る限りでは国会図書館にしか所蔵されていないんですよ。おまけについこの間までは小さなマイクロフィルムに、今はデジタルデータにされちゃって、どちらにしてもモノクロの粗い映像でしか見られない。ほおらこの通り、本物の表紙はカラーですよ。銀で刷った秋草風の模様の上に、わざわざ厚めの紙に別刷りにした小室翠雲の南画を貼り付けてある。さずが五周年誌、贅沢な造りだねえ。これは中国の高級食材のケツギョかしら。口絵は日本画の竹内栖鳳と洋画の林重義だね。栖鳳の画題はお得意のカツオだ。活きがよさそうじゃないですか。


何をそんなに興奮しているのかって? ですから、あの戦前の名店「花の茶屋」の機関誌なんですってば。なにせ花の茶屋は文学史の大事な舞台なんですよ。本山荻舟や長谷川伸、直木三十五、江戸川乱歩らが大衆文学を世に認めさせようと立ち上げた「二十一日会」の会場でしたし、芥川賞と直木賞は花の茶屋での会議で生まれたんだから。今でこそ選考会会場は「新喜楽」だけど、時が時ならこの店で開かれたっておかしくないくらい。それが証拠にここにほら、文芸春秋社主の菊池寛も直木三十五も文章を寄せているでしょう。文芸春秋社は昭和2年に麹町から内幸町のダイビルのところに引っ越してきたんで、社員がよく使うようになったのかも。ちなみに花の茶屋があったのはね、今の日比谷シャンテ前の広場あたり。このほかに内幸町の日比谷セントラルビルの裏あたりに支店も開いているしね。
そもそも花の茶屋主人の井上太四郎といえば、丸の内あたりじゃあちょっとした顔だったんですよ。ここに井上がモデルになった割烹着姿の彫像の写真があるでしょう。作者は日名子実三。柴田書店から歩いていけるところにある、日本サッカー協会のシンボルマークの八咫烏をデザインしたのはこの彫刻家なんだから。


それがどうしたですって? じゃあ、東京音頭ならご存じでしょう? あの夏の定番曲はもとはといえば井上太四郎たちが考えついたんですよ。夏といえば田舎に行けば盆踊りがあるが東京にはない、ここは一つ丸の内の繁栄のために街の音頭を作ろうってね。心意気が嬉しいじゃありませんか。このアイデアは芥川賞と違って風呂屋の朝風呂で生まれたそうで、席上(湯船中?)にいたのは井上のほか、西洋料理の「松本楼」の主人だったと作詞担当の西條八十が戦後『唄の自叙伝』で回想してます(『西條八十全集17巻所収』)。もっとも作曲担当の中山晋平は昭和10年の東京日日新聞で、一緒にいたのはおでんで有名な「富可川」主人だったと答えてる。まあどちらにしても井上が関わっていたのはまちがいないでしょう。昭和7年夏に日比谷公園で踊られたこの丸の内音頭を、10月に東京市が大拡張されたのに合わせて翌年替え歌にした。それが今の東京音頭ってわけ。この拡張以前は東京は15区で、品川も目黒も世田谷も大森蒲田も渋谷も中野も豊島も荒川も板橋も足立も葛飾も江戸川もみーんな郡の一部だったんだからね。
おいおい、東京音頭も知らないの? 弱っちまったなあ、現代っ子てのは…。あのね、今もコンビニで売っている「週刊朝日」って雑誌があるでしょう。あれは大正の創刊当時はふた周りくらい大きなサイズのグラフ誌っぽい造りで、アメリカで活躍していたジャーナリストの翁久允を編集長に迎えたハイカラな雑誌だった。井上太四郎は翁と知り合いでね、当時の週刊朝日にしちゃ珍しい料理記事を寄稿してるし、彼にいろんな文化人を紹介してもらったんですよ。もともと彼は顔が広くてね、この雑誌の表紙を描いた小室翠雲に同行して北陸旅行をしたり、富可川主人が発行した小冊子「おでんの話」に松崎天民らと共に寄稿したり。芸術家の岡本太郎がご両親の岡本一平とかの子と一緒にヨーロッパに渡ったとき、送迎会は花の茶屋の箱根支店で開いたんだから。あの柳田國男だって『味冴』の別の号に、「花の茶屋 楽書」って文を寄稿しているし。私にとっちゃ雲の上みたいな古本蒐集の大家、斎藤昌三が報告しているんで『定本柳田國男集別巻5』にはこのタイトルのみ収録されてますけどね、文章そのものは行方知れずなんですよ。だから昭和3年の「味冴」だったら、いったいどれくらいの価値があるか…。あ、この号はいくらしたかっていうと4200円。まあ1万円出したって惜しくはありませんけどね。
え、ここに1000円って書いてあるって? やだね、めざとくて。実はねえ、抽選に当たった雑誌を入り口で受け取って、ほくほくもので即売会の会場に入ったら、いま見たばかりの表紙がこっちを向いて棚にちょこんと置かれてたんですよ。そりゃあ、たまげたねえ。帳場の人に変な顔をされたけど、無視して両方とも買いました。そっちは1000円だったんだけど、ひとケタまちがっていたのかねえ。
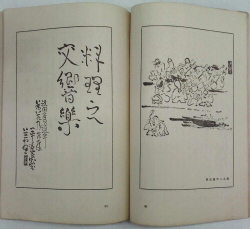

なあんだ、ほんとはそんなに珍しい雑誌じゃないんだろうって? うーん、もしかしたらそうなのかなあ…。大学や公立図書館の蔵書目録に載ってないだけで、学者先生の研究室や書斎には結構転がっているのかなあ。なにせ花の茶屋には、島崎藤村が田山花袋を誘って食事に行っているんだよねえ。そのときのお誘いの手紙は『藤村全集17巻』に載っているし、藤村は花の茶屋をモデルに『食堂』って小説も書いているしねえ。
食堂なら青空文庫に入っているからパソコンで読めるって? まったく、変なことには詳しいんだから。デジタル世代ってぇ奴かい? 本もろくろく買わないで画面でばっかり文字を追ってちゃいけませんよ。「器は料理の着物」って、どっかの人が言ってたろう? 本もおんなじですよ。ただ食べるだけなら使い捨て容器、ただ文字を追うだけならデータのほうが楽で便利だけど、こうして現物の風合いに触れたり、今日はどれくらい読んだかなぁってページの厚さで進み具合を確かめたり、顔の上にのっけて居眠りしたりするのもまた読書の楽しみなんだから。ブログなんてぇ代物を読むのもね、たいがいにしたほうがいいですよ。
だいたい食堂はちょっと可哀想な作品でね。同時期に書かれて同じ単行本に収録された「嵐」がうんと注目されたもんだから、島崎藤村の作品の中じゃあ脇に追いやられちゃった。食堂は新潮文庫の『嵐・ある女の生涯』には入っているものの、巻末の解説はやっぱり嵐中心で、一言も触れてもらえてない。嵐は岩波文庫にもなっているけど、これにいたっては食堂をはずしているからね。そういう事情は本の形で現物を見ないとぴんとこないかもね。
デジタルの食堂は全部読んだかい? ほおらみなさい、いつでも簡単に読めると思うと逆になかなか読まないもんだろう。いいかい、主人公のお三輪さんは京橋の料亭「小竹」の女将でね。関東大震災ですべてを失って浦和に避難してたんだけど、復興途上の東京で息子の新七が独立したもんだから、震災から1年経ったのを機に彼の新店を見にいくっていう話さ。福岡の新聞に連載されたのは震災から4年ちょっと後だから、当時の読者にとってはついこの間の話という設定だね。お三輪さんが震災の際に逃げのびた先が、たまたま店で7年間奉公していたお力と金太郎夫婦のもと。それがきっかけで新七は彼らとともに、従来の割烹店とも違った新しい形の“食堂”を始めたっていう筋書きだ。
「お三輪は震災後の東京を全く知らないでもない。一度、新七に連れられて焼跡を見に上京したこともある。小竹とした暖簾の掛っていたところは仮の板囲いに変って、ただ礎(いしずえ)ばかりがそこに残っていた。香、扇子、筆墨、陶器、いろいろな種類の紙、画帖、書籍などから、加工した宝石のようなものまで、すべて支那産の品物が取りそろえてあったあの店はもう無い。三代もかかって築きあげた一家の繁昌もまことに夢の跡のようであった。その時はお三輪も胸が迫って来て、二度とこんな焼跡なぞを訪ねまいと思った」
「《あれから、お前さん、浦和へ着くまでがなかなか大変でしたよ》とお三輪も思わず焼出された当時の心持を引出された。《平常(ふだん)なら一時間足らずで行かれるところなんでしょう、それを六時間も七時間もかかって……途中で渡れるか渡れないか知れないような橋を渡って……浦和へ着いた頃は、もう真暗サ。あの時は新七が宿屋を探してくれてね。その宿屋でお結飯(むすび)を造ってくれたとお思い……子供がそのお結飯を見たら、手につかんで離さないじゃないか。みんな泣いちまいましたよ……》」
今こうして読むと、ちょっと身につまされるところ、感じ入るところがあるね。震災で奪われた店と江戸の香りの残る街の思い出。そうしたものを踏み越えて新しい道に進もうとする店。料理業界の人にはぜひ読んでほしいねえ。ここに出てくる新七が開いた芝公園の「池の茶屋」のモデルが、「花の茶屋」ってわけ。
そうそう、話が後先になるけど「花の茶屋」は開業当時は芝公園の弁天池の向かいにあったんだよね。“芝公園の花の茶屋”ってきいて、公園の中で団子や飲み物を売ってる売店を想像する人がいるかもしれないけど、そりゃ“飯店”を一膳めし屋と思うのと同じくらいにそそっかしいからね。芝公園てのは住所のことだし、ささやかだけど、京都の丸山公園の茶店風に茶道具などを並べて、素人料理ながらもおでんに鍋、鯛ちりだって出していたんだから。それが震災後に、中国風の調度に変えて一品料理の店として営業し始めた。ほら小説にも、こう書かれているでしょう。
「お三輪は椅子を離れて、木彫の扁額(がく)の掛けてある下へも行って見た。新七に言わせると、その額も広瀬さんがこの池の茶屋のために自分で書き自分で彫ったものであった。お三輪はまた、めずらしい酒の瓶が色彩として置いてあるような飾棚の前へも行って見た。そこにも広瀬さんの心はよく働いていた。食堂の片隅には植木鉢も置いてあって、青々とした蘭の葉が室内の空気に息づいているように見える。どことなく支那趣味の取り入れてあるところは、お三輪に取って、焼けない前の小竹の店を想い起させるようなものばかりであった」
これだけ細かくディテールが描かれているのは、実際の花の茶屋が参考になっているからでしょうね。ちなみにお力夫婦は井上イチと太四郎のことだけど、新七はたぶん中村竹四郎がモデルじゃないかなあ。
それじゃあ広瀬先生のモデルは誰かって? そりゃほれ、星岡茶寮を開く前の北大路魯山人にきまっているじゃあないですか。(この項続く)
投稿者 webmaster : 2011年06月28日 12:08